小学校受験では数の数え方、数の順序、数量の比較など基本的な”かずの感覚”が非常に重視されます。市販の教材で何か良いものはないかと探している方におすすめなのが、「くもんのかずカード」です。
本記事では「くもんのかずカード」を実際に使ってみた感想や遊び方など詳しくレビューしていきます。
くもんのかずカードとは?
商品名 くもんのかずカード
発売元 くもん出版(KUMON)
対象年齢 3歳~6歳
数字と数量を視覚で結びつけられる知育カードとして、販売数も非常に多いロングセラー教材です。
数字が書いてある面とドット(●●●)で書いてある面があり、このドットの面がかなり使えます。実際の試験では数字ではなく〇を書きましょうという問いがあるため、このドット面で数の概念を覚えると本番に強くなります。
くもんのかずカードの遊び方と使い方
「かずカード」は自由度が高く、さまざまな使い方ができます。
特におすすめの小学校受験向けの活用法を紹介します。ここでは数の概念を学ぶため、1から9までのカードを使用していますが、余裕があればもっと大きな数字を使っても良いです。
数字を比べる
・1から9までのかずカードを使う(ドット面でOK)。
・2枚並べてどっちが大きい(または小さい)か当てる。
このゲームをすることで、かずの大きさなど「数の概念」が定着します。また、フラッシュカードとして使って数を覚える方法も効果的です。
数字の順番を並べる
・1から9までのかずカードを使う。
・カードを1から順番に並べる。
・「〇番目は?」「〇番目の前は?次は?」と問いかけてあげるのも◎。
数字を並べることにより順序問題に強くなります。
合成・分解ゲーム
・1から9までのかずカードを使う(ドット面でOK)。
・カードを使い、「3と2を合わせるといくつ?」、「3はいくつといくつに分けられる?」と問いかける。
数を足したり、分けたりすることで加法、減法を学びます。ドット面を使うことで視覚的にどれだけ増えたり減ったりするかがわかりやすくなります。
小学校受験に役立つ3つの力
「くもんかずカード」は、以下のような受験で重要な思考力の土台を育ててくれます。
数量認識 数字と数量を一致させる力
順序理解 数の並び・順番を把握する力
合成・分解 数を作る・分ける力
小学校受験で頻出の「いくつあるか答える」問題や「〇番目」などの順序問題に役立つ力が育ちます。
実際に使ってみた体験談レビュー
ここでは私が実際に使った感想をレビューします。
うちの息子は数の認識が弱く、概念が理解できていませんでした。最初はドット面を使い、「1は〇が1つ」という数字の理解からはじまりました。
このドット面が数を教えるのに非常に優秀で教えやすく、子どもも理解しやすいようです。
数字を理解してからは、数字の順番や合成・分解などのゲームをしながら数の理解を深めていきました。
カードを何枚か持ってきて「○○行の電車のホームは何番でしょう」など自分の好きな電車のクイズに使ったりと遊び方は無限大です。
ゲーム感覚で楽しみながら数を教えられるのでとても使いやすかったです。
総合評価(5段階)
知育効果 ★★★★★
遊びやすさ ★★★★☆
コスパ ★★★★★
対象年齢の幅 ★★★☆☆
小学校受験に直結する「数の基本」が育ちます。ルールも簡単で小さいお子様でも無理なく遊べます。6歳くらいまでは遊べますが、それ以上になってくると物足りなくなってくると思います。
あくまで小学校受験対策用かなという印象でした。
まとめ。かずカードで”算数の芽”をやさしく育てよう
数に強いとは計算が速いと思われがちですが、それだけでは不十分です。受験問題では数の概念を「感覚としてつかんでいるか」「頭の中でイメージできるか」といったより深い理解や柔軟な思考が問われます。
その力は決して一夜漬けでは身に付きません。毎日の何気ない遊びの中で少しずつ育てていくものです。
「くもんのかずカード」はまさにそのような力を育むのにぴったりの教材です。
ゲームを通して数字を視覚的にとらえ、体感的に覚えることができます。大人が教え込むのではなく、一緒に楽しみながら学べるという点がボードゲームで学ぶ最大の魅力だと思います。
「学ぶってたのしい」「わかった!がうれしい」という体験の積み重ねがやがて本番での思考力・集中力・表現力へとつながっていきます。
今後、算数が「好き」「得意」と感じている子は受験だけではなくその先の学校生活でも自信を持って学べるようになります。
「数が好き!」の気持ちを、今、育てておくことが未来への一番の準備です。
「くもんのかずカード」はその第一歩として、親子にとって優しい味方になってくれるでしょう。

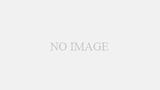
コメント